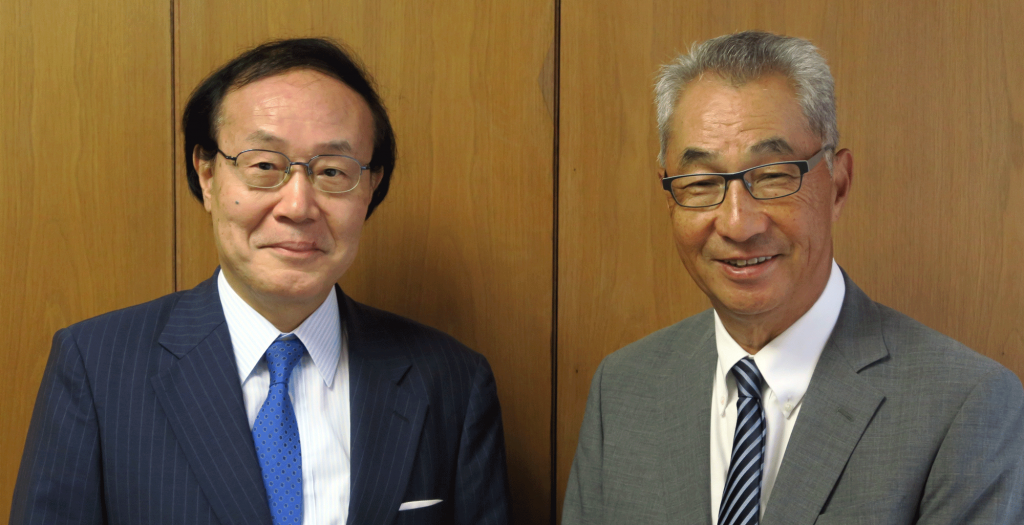
ゲスト:全国信用協同組合連合会(全信組連) 理事長 元 金融庁 総務企画局長 内藤 純一(左)
| プロフィール | 1951年生(兵庫県出身)。75年東京大卒、同年大蔵省(現在の財務省)入省。 その後、銀行局銀行課長、東海財務局長、証券取引等監視委員会事務局長、金融庁総務企画局長などを歴任後、2011年6月より現職。 経済学博士(名古屋大)。 |
|---|
――内藤さんは、長く金融庁にいらっしゃいました。異次元緩和と言われるマイナス金利の中で、金融機関はどのようなことが求められるのでしょうか。
内藤:1月にマイナス金利の導入が決定し、2月から実施されました。マイナス金利の決定以後、日銀に銀行等の金融機関が預ける預金は3層構造に分かれることになります。一定の範囲の預金については従来通りプラス0.1%が適用され、2番目のゾーンは0.0%が適用となります。そのあとの残りについて-0.1%のマイナス金利が付されるのです。できるだけはみ出る超過預金を減らさせるペナルティになる訳で、金融機関は当然それをどこかに持っていこうとすることになります。どの金融機関も、-0.1%の適用を受けないよう、その資金を短期の金融市場などで運用することになるため、資金はその他のマーケットに流れますので、当然ながら金利は下がります。以前であれば、金融緩和するとまず預金金利が下がるため、預金と貸出金の間の利ザヤは拡大しました。この利ザヤ、すなわちスプレッドの拡大によって金融機関全体の利益を生むことになりました。
インセンティブ、つまり元気が出る訳です。元気がついて、少しリスクの高いところにでも貸そうじゃないかという競争が金融機関の間で起きることで金融全体が活発化していくのです。また、借り手の側でも、金利というコストが低下することで借り入れ意欲が高まるという変化も生まれました。これが従来の金融緩和波及のパターンだったのです。

――いままでの金融緩和と違うところはどのようなことでしょうか。
内藤:今はすでに預金金利はほぼ0に張り付いています。これをマイナスにしようとか、手数料をかけて実質マイナスにするという議論はありますが、なかなか簡単ではありません。一般のお客さまに対してマイナス金利をとると、預金を引き出そうという動きになります。これが大規模に起こると、金融機関の資金が大量に流出するため、今度は金融不安の懸念が生まれます。
だから、預金金利は0を割り込んで下げる訳にはいかないのです。一方、借り入れをしているお客さまは「金利が随分下がっているのだから、住宅ローンなどの借入金利をなぜ下げてくれないのか」と言い始めます。すると競争相手の金融機関が「少し安い金利でお貸しします」と言い出します。こうなると、お客さまは「あなたのところも、もっと下げてくれないとあちらに行くよ」となります。仕方がないから「うちも下げましょう」となって金利下げ競争が始まり、貸出金利は下がっていくのです。
金融機関は当然ながら、その営業経費などは簡単に削れないため、結局収益が落ちてしまいます。以前の金融緩和は金融機関の元気を出す政策だったのですが、今は元気が出なくなる政策となってしまいました。
――銀行も貸したいけれど、お金のやり場が無い。世界中がそのような状況ですね。回らないで滞っているような感じがします。
内藤:そうです。金利が安くなったから個人は「住宅ローンを借りようか」とか、企業は「設備投資をしようか」となってきたら景気に元気が出てくるはずです。日銀はそれを狙っていますが、少なくとも今までのところ、そうはなっていません。何故かというと、住宅ローンをするかどうかは金利水準だけでなく、将来の給与の伸びや税金、年金など人生設計全般の行く末にかかわってくるからです。
 また、勤労世代もどんどん数が減り、昔のように団塊の世代が、どんどん郊外に家を建てた時代とは違います。設備投資も金利が下がって、爆発的に増えるなんてことはありません。なぜなら、多額の内部留保を蓄積している会社が多いため、お金を借りる必要すらないからです。
また、勤労世代もどんどん数が減り、昔のように団塊の世代が、どんどん郊外に家を建てた時代とは違います。設備投資も金利が下がって、爆発的に増えるなんてことはありません。なぜなら、多額の内部留保を蓄積している会社が多いため、お金を借りる必要すらないからです。
消費も若い世代の人は、子供の育児や教育費などがありますから、自由に使うお金の余地がない。個人金融資産の圧倒的に大きな部分を占める中高年層は、年金の運用や色々な金融商品に投資をしていますが、利回りは大きく下がり、預金も金利はほとんどゼロ。社会保障の実質負担が高まるなか、年金生活者の運用収入は確実に下がっています。こうして、個人消費も伸びる環境にはないのです。唯一好ましい変化をあげるとすれば、それは外国人観光客などによるインバウンド消費でしょう。
――そんな中で金融機関は、投資信託や保険などの資産運用に力を入れています。
内藤:我々の信用組合業界では、一部の信用組合は熱心に投資信託や保険の窓販をしていますが、総じて信用組合は小さな金融機関であり、投資信託や保険商品を販売するとなると、お客さまに対する説明責任など重い責任が課されます。しかし、それに当てられる要員が限られるために、そこを大きな収益源にしていくには難しい事情があります。一方、大きな金融機関の場合はむしろ本業の預貸業務の収益が落ちているため、なんとか手数料を稼ぎたいということで投信に力を入れる。あるいは保険商品に力を入れる。ごく最近は投信よりも保険商品に力を入れていますね。手数料が高いからということなのかもしれません。
――そんなところに金融庁から、フィデューシャリー・デューティや手数料の開示など厳しい話がでています。
内藤:関係する業界は大変なようです。投資信託や保険商品に力を入れるのは、本業である預貸業務の利ザヤが薄くなるなか、金融商品の販売手数料がますます魅力的に見えてくるからです。
日本の場合、預金が圧倒的に大きく、個人が持っている金融商品の52%程度が預金です。預金はこれだけ金利が下がっても、大多数の皆さんは手を付けず、そのまま置いています。消費者動向をうかがう調査によれば、元本が毀損しない商品は今でも圧倒的に人気があります。株や債券は値の変動があります。
債券の場合は、今までなら満期まで持っていれば元本満額が返ってきましたが、マイナス金利の導入後は、多くの国債利回りがマイナスになった関係でそうはいかなくなってしまいました。また、株には時価の変動があり、特にこの年以来、多くの株価が大幅に低下したことは申し上げるまでもないでしょう。このような状況にあるため、やはり預金を相当な割合で持たなければいけないと皆さん思うわけです。銀行にとってみれば、投資信託や保険商品を買ってもらって手数料を稼ぎたいのに、そのまま預金で置いておかれる。ほぼゼロ金利の状況では、預金者はもちろんですが、金融機関にとっても苦しい状況が続いているのです。
――保険についての考え方も変わってきました。
内藤:終身生命保険は、ご主人が亡くなった後、奥さまやお子さんに保険金が支払われることをメインシナリオにした、ある種ハッピーエンド型ともいえる商品です。ただ、今は長生きなので、80代、90代の方がたくさんおられます。そうすると、お子さんも相当な歳になります。以前は、まだ小さなお子さんがいる一家の大黒柱が亡くなると、収入ががくっと減るのでそれを支えるのが生命保険の主な仕事でした。しかし、長生きの方が多くなると、介護など今までになかった問題が出てきます。普通の生命保険や医療保険だけではカバーできないものもあります。
ところが、息子や娘もいい歳だし、あまり迷惑もかけられない。自分たちが子供に遺産を遺すのではなく、自分たちのために使うことで、子の世代、孫の世代に迷惑をかけないようにしようと。これが、今の商品設計の主流になっているようです。ですから、60歳から、あるいは、70歳、80歳でも入れる保険というのが今の売り文句ですね。掛け捨ての損害保険感覚ですね。昔とは保険の考え方が変わってきているのです。
――高齢者の方が入る保険や購入する金融商品が増えてきています。ある証券会社の幹部の方に聞いたら、「お客さまは高齢者です」と、はっきり仰っていました。

内藤:日本の場合、個人金融資産の65%程度を60代以上の人が保有しています。中高年の人たちとの間で金融商品に関するトラブルが頻繁に起きているといっても、お年寄りにいい加減なことを言って騙し、それでトラブルが起きるんだろうと思われるかもしれませんが、それだけではありません。もちろん、そういう場合もあるでしょうが、そもそも60代以上の世代でないと投資信託も保険商品もそれほど多くを買えない、というのが今の日本の実情なのです。このため、金融機関の側でも大事なお客さまと見ているのがまさしくそういう世代であり、そこで、当然ながら、トラブルの起きる頻度も高くなることになります。
――今の金融庁長官がフィデューシャリー・デューティーと手数料の開示に関して、本腰を入れていると聞きました。
内藤:フィデューシャリー・デューティーは、投資信託とか保険商品に関して金融庁が以前から話しているテーマです。保険商品も色々な商品があります。通常の保険商品は、かかる事由が発生したら保険金をもらえますがそれ以外は駄目ですとか、告知義務を果たさなかったらもらえませんなど、割合明快です。
しかし、変額年金と呼ばれるような投資性のある保険商品もあります。保険のサービスと同時に投資信託的な要素があって、2階建てになっています。こうなると、話は複雑になってきます。何に運用しているのか、また、どのように運用するのかなどすべてが結果に繋がってきます。このため、投資運用業者はお客さまのために忠実に業務を行わなければならないとする忠実義務、言い換えれば、フィデューシャリー・デューティーと呼ばれる受託者責任などが金融商品取引法の中に規定されているのです。
さらに、預金は誰にでもすぐわかる商品ですが、金融商品というリスク性のある商品については、いわゆる適合性の原則も同法に定められています。金融商品を販売する業者は、それぞれのお客さまの知識や経験とか、財産の状況や投資の目的とかをよく見て勧誘をしなければなりません。それに合わないような商品は販売すべきでない、という大原則がフィデューシャリー・デューティーです。
――金融商品は「わかりにくい」ものが多いです。商品もわかりにくいし、収益構造もわかりにくいですね。初心者は、おまかせ状態になってしまいます。
内藤:以前、私が証券取引等監視委員会の事務局長であった時代に問題になった事案がありました。具体的には、不動産投資信託の上場リートについてです。リートの運用態勢、とりわけガバナンスやコンプライアンスの適切性という観点から監視委員会は日々検査を行っています。
いうまでもなく、リートの不動産運用会社は、お客さまから預かったお金を不動産物件に投資をして、回収した家賃収入等をお客さまに還元することが業務の基本です。しかし多くの場合、運用会社の上には親会社の不動産会社があります。それらの多くは大手の不動産会社です。リートという仕組みがまだなかった時代には不動産会社が直接銀行からお金を借りてビルを買い、テナントを入れ、受け取った家賃収入で返済していくスキームでした。すると不動産会社自身のバランスシートがどんどん大きくなってしまい、財務管理上、さまざまな問題を引き起こすことが懸念されるようになってきました。
そこで、このような投資資金はできるだけ不動産会社のバランスシートの外に出したい。そうしたニーズを汲んでアメリカでも行われている合理的な手法であるリートを法制化したというわけです。このリートを実際に立ち上げるとなると、不動産会社の外に運用会社を子会社として設立し、一般の投資家の資金を集めて不動産物件に投資する、ということになってきます。とはいえ、全体の不動産の購入戦略とか運用にかかる基本戦略とかは、親会社である不動産会社が携わる最も重要な業務であることは論をまちません。こうした実態があるから、この不動産運用会社にはお客さまのためのフィデューシャリー・デューティー、つまり受託者責任の履行が強く求められることになってくるのです。
上場リートであれば、資金は市場の一般投資家のお金が主なものでしょう。しかし、実際に資金を運用する主な人は、不動産についての専門的知識をもった親会社から出向してきた人たちです。ここに問題発生の原因が潜んでいるのです。投資には常に失敗や損失がついて回ります。損失も投資家が被るべき損失であれば、これは仕方ないのですが、投資家が本来被るべきでない損失、例えば親会社なり運用会社が自らの錯誤や判断ミスなどで失敗し、それによる損失が大きく膨らんだ時、それをお客さまの損失として付け回すようなことが想像できるのです。
一方、想定外の利益は都合よく親会社の利益にカウントするとか。こうした利益相反行為は大いにありがちです。何故かというと、社長も親会社から派遣されてきていますから、親会社に対して良好な成果を出すことを求められているからにほかなりません。言い換えれば、一般投資家を蔑ろにする。さらに言えば、そういうことが外から見えないという点に根深い問題があるのです。この隠された部分をチェックするとなると、監視委員会のような、検査という形で入らない限りなかなか見えてこない。それが残念ながら、いくつかの事案からうかがわれる実態の一部というしかありません。こうした意味から検査はもちろん重要ですが、もっと大事なことは、金融商品取引業者がわきまえるべき基本精神でしょう。果たすべき責任をきちんと果たす、つまり、フィデューシャリー・デューティーの精神にほかなりません。他からチェックされるまでもなく、自身がそういうことをきちんと遵守するという考え方です。
――誰のために運用をするのかということですね。
内藤:親会社のために仕事をするのではなく、お客さまのために仕事をすべきだということです。仮に親会社が損害を受けるようなことがあったとしても、受託・委託の関係でお金を出す相手は一般投資家です。一般投資家のために最善のことをやるべきだというのが、ここでいう原則なのです。
今行われている議論について詳しい話を承知しているわけではありませんが、販売者である銀行や保険会社がリスク性のある金融商品を販売する時に、手数料の高いものを勧めているのではないか、という疑念にもとづく問題が指摘されています。そのため議論が少し広がっているようですね。
お客さま本位という意識が失われてしまっているのではないかという点が、そこで問われるべき最大の問題なのでしょう。フィデューシャリー・デューティーないし忠実義務、そして、善管注意義務や適合性の原則などは法律の世界に属しますが、本来、法律さえ守ればそれでいいのだということではなくて、望ましい原則はもっと広い概念であるはずです。それが、つまり、お客さま第一主義、お客さま本位の営業姿勢という考え方で、それはもう一段高い営業道徳なり営業哲学をめざすべき、という話になってくるのです。
――金融商品を販売する時には、色々な説明責任があります。その時、情報を正しく、わかりやすく伝える「情報品質」は重要なことだと思います。

内藤:先日のUCDAアワード2016実行委員会の時にお話ししたのですが、ある会社の説明文書が以前は割合シンプルで、非常に「わかりやすい」と評価を得ていた。ところが、最近、その評価が落ちてきた。なぜかというと、今までの説明条文や条項の間にさらに別の文章が入るなど、色々なものが増えてきたからです。
枝葉が増えてきたんですね。「それは何故なのか」と私がお聞きした時、事務局の方の話では、「わかりやすさを追求したけれど、営業の現場でトラブルが起きたりすると、お客さまから『そんな説明はここに書いてないじゃないか』と言われてしまい、さらに大きな問題になってしまう。きちんと対応策を考えておかないと会社や社員を守れないからという発想でどんどん増えてしまったのだ」と。
つまり、こうした事情で「わかりやすさ」がどんどん抜け落ちていくんですね。「わかりやすさ」は大事ですが、そもそも、誰にでも「わかりやすく」、かつ、内容的に完全無欠の文書なんてものは、ありえない訳です。粗探しをすれば、必ず欠陥は出てきます。わかりやすさを会社としてどう考え、絞り込むかということに尽きるのです。
文章を作る時、一つのパターンで作らざるを得ませんね。けれど、適合性の原則というのは、相手によって、相手の様子や事情を勘案しながら説明に工夫を凝らしなさいということです。勧める金融商品も色々と選択的に考えなさいと法律は言っています。でも、法律の精神を完璧に守ろうとすると、今度は営業現場が困ってしまいます。かつて金融商品取引法を施行した直後、いささか混乱が起きました。説明責任をきちんと果たさなければと真剣に考えた金融機関があって、70歳以上の方に徹底的にリスクの所在などを説明する方針を出したことで、お客さまと営業現場からもの凄い不満が来たんです。金融機関で投資信託を買おうとしたら、「全部説明させてください」と、分厚い書類で延々説明を受けたと。
――私も10年くらい前にドル預金を銀行でやろうとして、銀行員に「あなたより詳しいから大丈夫だ」と言いましたが、駄目だと言われました。
内藤:本当はそれこそが適合性の原則に基づくべき事柄であって、相手の知識・経験などに応じて対応を柔軟に変えなさい、というのがこの原則の中身です。ところが、営業現場では、同じ説明文書で正確にチェックしないといけないというお達しが金融機関の本部から来ている。これが新しい金融商品取引法の精神であり、金融庁はそれをやれと言ったじゃないか、と。
ところが、金融庁では、そんなところまでは言っていない。それを過剰解釈し、過剰反応したのではないのかということで議論が起こり、現場でも多くの混乱がありました。それから少し経って、行き過ぎだと明らかになって収まりました。
いずれにせよ、投資家や消費者、利用者から寄せられる一番大きな声は、説明文書が多すぎるというものです。延々と説明を受けたが、結局はよくわからない。それでは、どうしたらいいのかというものなのですが、これに一つの正解はありません。
――携帯電話でも同じような現象が起きています。使わない機能のことでもきちんと説明を受けないといけないとか。とても時間がかかります。
内藤:携帯電話の場合も契約ですから、金融と同じ問題が出てきますね。おまけに商品の機能が複雑になってきましたから、説明に時間がかかります。商品の機能が人間の理解力を超えていますね。ここでも、トラブルがあったときにどういう対応を取るのかが非常に大事です。金融では、金融商品取引法が施行されて以降、投資者保護のための関連規定や制度などが色々と整備されてきました。
たとえば、そのなかでの大きな改革として、金融ADRという制度の創設が挙げられます。金融の世界ではトラブルが起きやすいのですが、その時、本来の裁判で争うほどの金額でもなく、また、そんな時間もないような時に、不満や苦情を持っていく受け皿を作ったのです。そこでは、きちんとしたルールに基づく手続きを経て双方の和解点を見出し、紛争を解決しようとするものです。もちろん、そこでの和解が全くできないということなら、裁判に訴えるしかありませんが。ADRというまさに裁判外の紛争処理制度。今では各業態にありますから、それ以前に比べると格段の進展だと思います。
――今、金融機関や保険会社では、お客さまの意向確認をどうするのか悩んでいるところもあります。紙が増えるとか時間が掛るとか。

内藤:金融機関も証券会社も保険会社も、それぞれ扱う金融商品は違いますが、お客さまとの関係において基本は顧客第一主義です。顧客第一主義、つまり、お客さま本位の営業姿勢を貫いていくしかありません。金融機関などが詳しい説明文書を作り、営業現場が一から十まで全部顧客に説明するというのは、お客さまにリスクを認識してもらうためというよりも、金融機関自身が自らのリスク回避のためにやっているのではないかと疑われるというものです。それではお客さま本位では無いのです。
お客さま本位は、この人のためにはどうしたらいいかを考えて、それに合わせた説明の仕方をするということ。大事なのは適合性の原則にほかなりません。そうした意味で、手数料が高い方を買わせるように仕向けるというのでは、お客様本位とは言えません。「これを買いたい」と明確に言ってくるお客さまはそう多くはありません。なんとなく買いに来たりします。そういうお客さまが金融商品のことを深く知っていないことは直感的にわかるはずなので、初心者コースの金融商品から話し出すということが大事でしょう。単純な商品がそのお客さまに合っていると思えば、まずはそれを勧めるべきです。
そして、そのような商品の手数料は本来、低いはずです。単純な商品を勧めると、説明も簡単になります。複雑な商品を簡単に説明しようとすると相当枝葉を落とさざるを得ませんから、そこに問題が生じる可能性が高まります。金融機関にとってリスクが高まりますが、買ってもらえば高い手数料が入ってくる。しかし、これはお客さま本位とはいえない。
――UCDAを始めたきっかけが「心のユニバーサルデザイン」という考え方でした。情報を送る側が、受け取る側の気持ちになって、情報を作らなければいけない。これが原点でした。そういう意味では適合性の原則という考え方に非常に近い考え方だと思います。
内藤:そうですね。顧客本位の考え方です。相手の立場に立って考える。そういうスタンスですね。お客さまの立場、それをフィデューシャリー・デューティーと呼び替えてもいいですが。金融機関が、そのような考え方で営業すると、トラブルも相当減ると思います。相手を考えながら対応していくべきということが金融商品取引法の考え方でもあるのです。
――最後に、内藤さんには2010年のアワードの時からずっと応援していただいていますが、UCDAに期待することなどありましたらお願いします。
内藤:今ではUCDという考え方が、証券・保険・金融の業界にかなり浸透してきたように思います。こうしたお客さま本位という視点は、言葉の説明を必要とする金融商品はもちろんですが、通信関係の商品や食品、医療関係など他の分野であっても、特に、今後高齢化がいっそう進む日本の社会では、UCDAの役割がますます重要になってくると思います。証券・保険・金融の分野からさらに拡大、発展していっていただきたいと思います。お客さま本位という考え方は、どの業種でも本来同じなのですから。
――アワードも「情報品質という大きな責任」をテーマにしています。「情報品質」は情報を送る側の企業も、それを形にする印刷会社、デザイン会社、システム会社の人たちも大事にしなくてはいけないですね。本日はありがとうございました。
