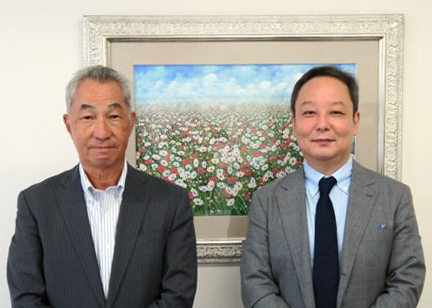
ゲスト:元日経デザイン編集長/株式会社コンシリウム 代表取締役 勝尾 岳彦(右)
| プロフィール | 1991年日経BP社入社。日経デザイン副編集長、日経アート編集長、日経デザイン編集長、日経ベンチャー経営者クラブ事務局企画編集部長などを経て、2016年3月末に同社を退社し、企画・デザインプロデュースを行う株式会社コンシリウムを設立。経済産業省「ユニバーサルデザイン懇談会」委員、埼玉県「彩の国 人にやさしいまちづくり賞」選考委員などを歴任。平成14年より内閣府バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者表彰制度選考委員会委員。 |
|---|
―勝尾さんは日経デザインの編集長でいらしたのですが、日経BP社へ入るきっかけは何だったのですか。
勝尾:大手デザイン会社で、4年間ほど企画や調査の仕事をしていました。そこを辞めた後、日経デザインという雑誌の仕事がしたくて、1991年に日経BP社に入社しました。入社した時はもう30歳を過ぎていたので、早く周りに追いつけるように現場でしごかれました。1993年に日経デザイン副編集長に昇格して1年ほどで1994年に日経アートという別の雑誌の編集長になり、98年に日経デザインの編集長として古巣に戻りました。
―編集の仕事についてお聞かせ下さい。
勝尾:日経BP社の場合は、スタッフライター制をとっています。記者が自分で書くのが基本です。最近では、外部のライターさんを起用することも多くなってきましたが、バックグランドが新聞社なので、社内の人間、編集部の人間が、記者として現場に取材に行って、ファクトを集めて記事を書きます。専門誌なので、読者の属性が割合はっきりしています。しかも直販ですので、どういう方が読んでいるのかわかる訳です。それぞれの読者の属性に合わせた内容を、できるだけわかりやすく深掘りをして書くのが基本です。
―記事の材料は記者の方が日々探しているのですか?
勝尾:日頃から色々な方々にお会いして、記事の企画を準備しておきます。そして、毎月の企画会議で提案をして、承認されたら記事を書きます。企画会議は編集長が中心になって采配をふるいます。まず、大雑把に1年間の毎月の特集スケジュールを決めておきます。2ヶ月程前に、どういう方向性で記事を作るのかを決めます。そこで、記者が提案したものを、編集長や副編集長、他の記者も参加して、企画や取材先を練っていきます。小さい記事では一人で書きますが、特集はチームで作り上げていきます。
―特集を組む際の基準と言うものはありますか。
 勝尾:読者の半分は、デザインの製作側、残りの半分は企業内で企画や営業、技術関係の仕事に携わっている方々です。日経デザインは直販の雑誌ですので、読者に毎月アンケートを実施しています。300通ほど送ると約3分の1が返ってきます。前号のどの記事がどれくらい読まれて、読者にどれくらい役に立ったのかを数値で分かるように整理しています。今どういう記事が求められているか、どういう切り口でいけば読者に役に立ったと実感してもらえるのかを分析しながら特集の企画を決めていきます。
勝尾:読者の半分は、デザインの製作側、残りの半分は企業内で企画や営業、技術関係の仕事に携わっている方々です。日経デザインは直販の雑誌ですので、読者に毎月アンケートを実施しています。300通ほど送ると約3分の1が返ってきます。前号のどの記事がどれくらい読まれて、読者にどれくらい役に立ったのかを数値で分かるように整理しています。今どういう記事が求められているか、どういう切り口でいけば読者に役に立ったと実感してもらえるのかを分析しながら特集の企画を決めていきます。
―1998年以降、日経デザインでUDを本格的に取り上げるようになったそうですが、社会的にも1990年代後半からデザインのユニバーサル化が言われるようになりました。
勝尾:高齢社会になることはだいぶ前から言われてはいましたが、UDはなかなか進みませんでした。1990年代の後半からやっと、高齢者対応ということでUDが重要になってきました。メーカーだけではなく、地方自治体や国もちゃんとUDに取り組まなくては、という意識が高まってきた時期でした。
先行したのは公共の空間だったと思います。人がたくさん集まる図書館や駅などです。最近では駅のバリアフリー化が進んで、ホームドアが増えてきました。それ以前は視覚障害の方など、ホームから転落して亡くなる事故が多かったですね。その後、家電製品や住宅のUD化にも各社が一生懸命取り組みました
―当時のUDとバリアフリーとの線引きはどうでしたか?
 勝尾:バリアフリーで努力をされてきた方々はたくさんいらっしゃいます。UDという言葉が普及する以前から、共用品推進機構が、障害者にも、健常者にも使いやすい製品を開発・普及するという、地道な活動を何年も続けていらっしゃいました。大手のメーカーの中にも、自主的に取り組んでいる方がいました。バリアフリーは障害者への配慮という視点ですが、ユニバーサルデザイン(UD)は、障害者も健常者もすべての人が対象になります。しかし、多くの人が暮らしやすい社会を目指すと言う点では同じだと思います。
勝尾:バリアフリーで努力をされてきた方々はたくさんいらっしゃいます。UDという言葉が普及する以前から、共用品推進機構が、障害者にも、健常者にも使いやすい製品を開発・普及するという、地道な活動を何年も続けていらっしゃいました。大手のメーカーの中にも、自主的に取り組んでいる方がいました。バリアフリーは障害者への配慮という視点ですが、ユニバーサルデザイン(UD)は、障害者も健常者もすべての人が対象になります。しかし、多くの人が暮らしやすい社会を目指すと言う点では同じだと思います。
1995年あたりから、ユニバーサルデザインという言葉が使われ始めていました。それ以前から、「日本は、高齢社会に突入する。その準備が必要」と言われていましたが、ようやく高齢社会への準備に真剣に取り組まなければならないという意識が高まってきました。今から20年近く前のことですね。誰でも年齢を重ねれば、若いころにはできたことができなくなります。高齢社会では、ものや設備、環境の作り方を変えていかないと、日々の暮らしの様々な場面で不自由な思いをする人がたくさん出てくるのです。
例えば工業製品の多くは30代から40代くらいの男性で、健常で理解力も、体力もある人を想定して作られていました。高齢社会を前提に考えると、その範囲に収まらない人がたくさんいるんです。その点を視野に入れて、多様な身体能力の人たちが、色々なものを使ったり、読んだりすることを前提条件とし、できるだけ自分自身で不自由な思いをしないですむ社会を実現するために、UDを誌面で取り上げていこうと決めました。それは自分のためでもあるんですね。自分自身も毎年確実に年をとるわけですし、祖父母や親のことを考えると決して他人事ではないわけです。
紙面で、パッケージは積極的に取り上げました。パッケージは日常的に使うものなので、ただ開けやすいだけでなく、力が弱い高齢者にも持ちやすく使いやすくなければいけません。表示も、食品アレルギーや医薬品の成分など生死にかかわる問題もあります。保険のパンフレットも取り上げたことがあります。保険は、家の次に大きな買い物と言われ、毎月、何十年間もお金を払い続けるので、非常に重要な商品です。なのに、誰も内容を理解していません。説明されても違いが分からない、内容が理解しづらいし伝え方も良くない。
携帯電話や家電製品、自動車のマニュアルや取扱説明書などもそうです。分厚い取扱説明書は誰も読まない。作り手を基準に書かれているので一般の方には読みづらいし、わかりにくい。それを改善する必要がある、という指摘は結構しました。インターネットは、新しいデザインのメディアとして取り上げました。そこでは、アクセシビリティを重要な要素として繰り返し取り上げました。
―その頃は、携帯電話のように新しい製品やサービスが生まれてパソコンが家庭にも普及し始めました。電子画面になると、アクセシビリティが中心になって開発されてきた印象があります。
勝尾:どれくらい簡単に必要な情報に到達できるか、それが適切に編集されているかが重要だと思います。それに関して様々なイベントやセミナーを開催してきました。UDのシンポジウムを2004年から毎年開催していますが、自動車メーカーや電機メーカー、住宅設備メーカーなど、様々な業種の方々にご協力をいただいてきました。日本は高齢化先進国などと言われますが、中国でも急速に高齢化が進んでいます。韓国や台湾などアジアのほかの国や地域、EU加盟の先進諸国も事情は同じです。ですから、UDは、莫大なマーケットだと思います。
―UDシンポジウムを2004年から続けてきて変化はありましたか?
 勝尾:UDへの取り組みが日本の社会全体で進んでくると、UDを声高に謳わないというところが出てきました。本来そうではないはずなのですが、UD=障害者、高齢者向けの製品だというイメージを持たれるのが嫌だというところもあります。また、UDは基本的な仕様として製品開発に組み込んだので、敢えてUDとい謳う必要は無くなったというところもあります。ですから、当然押さえておくべき基本性能として使いやすさには真剣に取り組んでいるのですが、表向きにはUDとは謳わない企業が増えました。
勝尾:UDへの取り組みが日本の社会全体で進んでくると、UDを声高に謳わないというところが出てきました。本来そうではないはずなのですが、UD=障害者、高齢者向けの製品だというイメージを持たれるのが嫌だというところもあります。また、UDは基本的な仕様として製品開発に組み込んだので、敢えてUDとい謳う必要は無くなったというところもあります。ですから、当然押さえておくべき基本性能として使いやすさには真剣に取り組んでいるのですが、表向きにはUDとは謳わない企業が増えました。
-カラーUDも近年かなり普及してきましたね
勝尾:日本では男性の20人に一人、女性の500人に一人が「色弱者」だと言われています。これらを合計すると、日本国内では約300万人の方々が色の知覚において他の方々とは異なる特性をもっていらしゃるわけですね。そういう方々は、交通標識や信号、教科書、電車案内図、避難経路図、家電製品のLED表示などの色の違いが判別できず、不自由な思いや危ない思いをされることがあります。
ここ十数年の間に、カラーユニバーサルデザイン機構(CUDO)などの地道な活動のおかげもあり、カラーUDも随分普及し、東京の地下鉄の路線図のように、色だけに頼らない情報伝達も増えてきました。また、九州産業大学の落合太郎教授は10数年前から、LEDの信号機の中にバツ印を付ける研究をされています。2年前に仙台で色覚障害の方が事故を起こされたケースがありましたが、その方はLED信号機の色の区別がつかなかったんです。改良型の信号機が採用され、普及すれば、こういう事故も減ることが期待できます。
―日経デザインで「読みやすさ」について気をつけていたのはどのようなことですか
勝尾:色遣いについてはもちろん配慮していましたが、フォントも大きくしました。あとは字間、字詰めにも気をつけました。対象読者の年齢はほぼ把握できるので、その方々に合わせて変えてきました。ただ、デザインの雑誌なのでバランスを考慮して調整しながら行っていました。
表記に関しては、なるべく読みづらい文字は開いて書くとか、カタカナ表記の使い方など日経新聞のスタイルブックに従っていました。話題は少しずれますが、最近、「本当に伝達手段が文章だけで良いのか」と思うことがあります。
例えば、難読症の方は文字を読むことが苦手です。その方たちに内容を理解してもらえるような手段を考えなくてはいけない。難読症の方は文字が読めないからといって、知能が劣っている訳ではありません。非常に知的水準が高い方もたくさんいらっしゃいます。米国のクーパー・ヒューイット国立デザイン美術館の館長をされていたダイアン・ピルグリムさんも難読症を克服された方でした。日本ではあまり難読症が認知されていませんが、何らかの対策を考える必要があります。
難読症のお子さんを持つお母さんにお話しを伺ったことがあるのですが、そのお子さんは、文章ではなく、YOUTUBEのような動画サイトの映像を見て内容を理解しているのだそうです。保険会社や銀行の契約書や、自治体の書式がそこまでできるかどうかはわかりませんが、ある程度は映像で理解してもらうようなものも用意した方が、親切だとは思います。
―UDという言葉でくくると、多くの人に使いやすい、わかりやすい、ということになります。高齢者、障害者、外国人などダイバーシティという視点では、この考え方も修正する必要があると思います。
勝尾:個別の人間にいかに対応するかになってくると思います。コミュニケーションの仕方も相手によって異なってくると思います。国際化が進んでいるので、それに対する変化も視野に入れる必要があると思います。UDという言葉が広まった時は、ひとつのもので対応できるという考え方をしていましたが、それは無理があります。個別のニーズに合わせて、いかにきめ細かな対応ができるかを考えなければなりません。
―UDが転換期を迎えていると言えますね。高齢化とグローバル化。2020年の東京オリンピックでは、試されますね。
勝尾:情報は毎年、同じものでも変わっていきます。法律が変わったり、サービスの変化があったりして。毎年修正が必要になります。そして個別のニーズに対応するために、細分化していくでしょうね。
―UCDAの活動でも、加齢対応の相談をよく受けますが、高齢者をひとくくりにすることはできません。何をもって高齢者対応と言うのか。ある程度の年齢をすぎている人を高齢者と呼ぶのか。そうではなく、ある状況で分けて細分化した人たちを指すのか。商品によって変わります。お客様を整理する必要があります。
 勝尾:まずは多様なニーズが存在すると、認識するところからですね。それから、マーケティング上では70代以上の人を対象にしているけれど、それをシニア向けの製品だと言って売れるかどうかはまた別の話になります。化粧品はイメージ的要素が高い商品ですが、最近の広告を見ていると、年齢の高い層を狙っているものが多くなったと感じます。でも、高齢者向けということは謳わず、機能的な部分を強調して幅広い層にアピールしています。また、シニアという言葉で高齢者をひとくくりにしてみても、身体能力や外見、気持ちの持ち方には一人ひとり大きな差があります。そこをどう分析し、一人ひとりのニーズにあったものを作っていけるかが鍵になるでしょうね。
勝尾:まずは多様なニーズが存在すると、認識するところからですね。それから、マーケティング上では70代以上の人を対象にしているけれど、それをシニア向けの製品だと言って売れるかどうかはまた別の話になります。化粧品はイメージ的要素が高い商品ですが、最近の広告を見ていると、年齢の高い層を狙っているものが多くなったと感じます。でも、高齢者向けということは謳わず、機能的な部分を強調して幅広い層にアピールしています。また、シニアという言葉で高齢者をひとくくりにしてみても、身体能力や外見、気持ちの持ち方には一人ひとり大きな差があります。そこをどう分析し、一人ひとりのニーズにあったものを作っていけるかが鍵になるでしょうね。
―高齢者の方々自身が自分たちが欲しいデザインはこうですと仮説をたて、それを改めていろんな身体能力の高齢者の方々自身が検証してズレを修正していったら、何か新しいものが生まれるのではないかと思います。
勝尾:UCDAの活動は前から知っていました。我々も保険会社のパンフレットを見て、改善していかなければ、不都合を被る方がたくさんいらっしゃるだろうとずっと感じていました。UCDAの地道な活動によって、保険会社や金融機関の一部ではありますが、取り組みが進んできたことは、日本社会にとって良いことだと思います。これからのUCDを考えるならば、文字以外の伝達方法についても、取り組まれるといいなと思います。
―映像や音声ですね。コミュニケーションの手段は文字だけではありませんから。その研究も進めていて、近いうちに提供できるようにしたいと思います。
勝尾:印刷物や電子媒体の画面では、UCDによる改善が進んでいると実感しています。これからは、コミュニケーションデザインとして、もっと総合的に取り組んでいかれることを期待しています。
―ありがとうございます。頑張ります。
